同じ美しい海を眺めているはずなのに、サーファーと釣り人の間では、残念ながらトラブルが絶えません…
お互いに海を愛する仲間なのに、どうして気まずい空気が流れたり、時には深刻な対立にまで発展してしまったりするのでしょうか?
不思議ですよね。
実はこの問題、単なる「マナーが悪い」という一言では片付けられない、根深い理由があるんです!
この記事では、どちらか一方を悪者にするのではなく、まずはお互いの言い分にじっくり耳を傾けてみたいと思います。
キャストしたルアーが人に当たらないかと心配な釣り人目線、そして見えない釣り糸に危険を感じるサーファー目線。
それぞれの立場を深く理解することが、解決への大切な第一歩だと考えています。
その上で、実際に起きてしまった悲しい事故事例からリアルな危険性を学び、それぞれのコミュニティに根付く暗黙のルールがなぜすれ違いを生むのかを考えます。
そして最終的には、いがみ合いを乗り越えて、お互いが気持ちよく海を楽しむための「共存」への具体的な道筋を、一緒に探っていきましょう!
- サーフィンと釣りの間でトラブルが起きる根本的な原因
- 釣り人とサーファー、それぞれの視点と正当な主張
- 実際に起きた事故事例と、お互いの暗黙のルール
- 今日から実践できる、安全に共存するための具体的な方法
サーフィンと釣りの間で対立が起きる背景
- なぜ同じ場所でトラブルが起きるのか
- 危険を避けたい釣り人目線の言い分
- 波を求めるサーファー目線の言い分
- ルアーやボードによる深刻な事故事例
- それぞれのコミュニティにある暗黙のルール
なぜ同じ場所でトラブルが起きるのか

THE Roots:イメージ
サーファーと釣り人の間でトラブルが頻発する最大の理由は、両者がそれぞれの活動に最適な場所として、全く同じ地形を求めているからです。
これは偶然ではなく、海洋物理学的な必然と言えます。
例えば、岸から沖に向かって強い流れが発生する「離岸流」は、釣り人にとってはベイトフィッシュ(小魚)が集まり、それを狙う大型魚が潜む絶好のフィッシングポイントになります。
彼らはこの地形変化を見つけると、そこに留まって集中的にルアーを投げます。
一方で、サーファーにとっても離岸流は、沖の波が良いポイント(ブレイクポイント)まで効率的に向かうための「自然の通路」として極めて重要です。
パドリングの労力を大幅に減らせるため、サーファーもまた離岸流の周辺に集まる傾向があります。
・ポイントの重複
このように、釣り人にとっての「聖域」と、サーファーにとっての「高速道路」が物理的に完全に重なってしまうのです。
問題の本質は、個人のマナー以前に、限られた優良な空間(資源)をめぐる必然的な競合関係にあると言えるでしょう。
お互いがそれぞれの活動目的を合理的に追求した結果、意図せずして同じ場所に集まってしまう。
この構造的な問題を理解することが、対立解消の第一歩となります。
危険を避けたい釣り人目線の言い分

THE Roots・イメージ
釣り、特にサーフからのルアーフィッシングは、多くの人が思う以上に、周到な準備と分析の上に成り立つ静的な活動です。
釣り人たちは釣行の前から潮汐表や風向きを読み解き、時には衛星写真まで確認して、魚が集まるであろう一級のポイントを予測します。
そして夜明け前から広大なサーフを歩き回り、ようやく探し当てたその場所は、単なる砂浜ではありません。
地形や潮の流れという自然からの情報を読み解き、「ここしか無い」と導き出した結論の場所であり、彼らの知識と努力が凝縮されたいわば「聖域」のような空間なのです。
この聖域(キャストが届く範囲)にサーファーが入ってくることは、釣り人にとって、仕掛けが絡まる、魚が散ってしまうという物理的な問題以上に、積み重ねた時間と労力、そして期待の全てが無に帰すように感じられるのです。
そして、そこから、より深刻な「安全」に関する問題も浮上してきます。
・「加害者」になるリスクという恐怖
釣り人が最も恐れているのは、自分の投げたルアーがサーファーに直撃し、大怪我をさせてしまう事故です。
釣り人は、自分の道具が意図せずして「凶器」になり得ることを自覚しています。
そのため、サーファーが接近してきた場合、事故を回避する責任は一方的に自分にあると感じ、強いプレッシャーに晒されるのです。
この「いつ加害者になるかわからない」という恐怖は、サーファーに対する過剰な警戒心や、時には先制的な排除行動につながることがあります。
彼らの厳しい態度の裏には、事故を未然に防ぎたいという自己防衛の心理が強く働いているのです。
波を求めるサーファー目線の言い分

THE Roots・イメージ
一方、サーファーの視点に立つと、世界は全く異なる様相を呈します。
彼らの行動は、刻一刻と変化する波や海流という、人間のコントロールを超えた自然の力に大きく左右されます。
サーフィンは本質的に動的な活動であり、その動きは予測が難しいものです。
一度波に乗れば、その進路を自由自在に変えることは困難ですし、沖に出る際には離岸流を利用するため、一直線に進むとは限りません。
このような状況下で、一点に留まる釣り人の存在と、そこから伸びる見えない釣り糸は、予測不能な障害物となります。
サーファーが感じる最も大きなストレスは、見えない脅威に対する脆弱性と恐怖です。
ウェットスーツ一枚の無防備な体で、水中や水面に漂う釣り針やラインに接触する恐怖は計り知れません。
ラインが首や手足に絡まれば、パニックに陥り溺れる危険性すらあります。
・公共の資源へのアクセス権
サーファーの視点からは、たった一人の釣り人が広範囲にキャストを繰り返すことで、そのエリア全体が事実上の「立ち入り禁止区域」のように感じられることがあります。
これは、多くの人が利用できるはずの良質な波という公共の資源を、一人が独占しているように映るのです。
彼らは波を求めて移動する権利を主張し、釣り人には他の利用者に配慮して場所を譲る柔軟性を期待しています。
ルアーやボードによる深刻な事故事例

THE Roots・イメージ
残念ながら、サーファーと釣り人の間のトラブルは、口論や不快感に留まらず、実際に深刻な傷害事故に発展したケースが複数報告されています。
これらの事故事例は、両者が互いに与えうる危険性の高さを物語っています。
・2021年 神奈川県茅ヶ崎市のヘッドランド(Tバー)周辺で起きた事例
この場所は、サーファーと釣り人の双方が集まる典型的な「危険が交錯する場所」でした。
ここで、サーフィンをしていた男性の右頬に、釣り人がキャストしたルアーが直撃。
ルアーのフックが頬を完全に貫通し、自力で外すことができず、病院で麻酔をかけて摘出する手術を受けるという痛ましい事故となりました。
被害を受けた男性自身がSNSで「あと数センチずれていたら失明していた」とその危険性を訴えたことで、この問題の深刻さが広く知られるきっかけにもなりました。
また、海外に目を向けると、投げ釣り用のオモリがサーファーの顔面に直撃し、顔面を骨折するという、さらに深刻な重傷事故も報告されています。
ルアーのフックが「刺さる」危険性だけでなく、硬く重量のあるオモリが「打撃」として加わる危険性も無視できません。
金属製のルアーや数十グラムのオモリは、時速100kmを超えることもあると言われており、人体、特に頭部や顔面のような急所に当たれば、その結果がどれほど悲惨なものになるかは想像に難くありません。
「海の地雷」問題
もう一つ深刻なのが、海中や砂浜に放置された釣り具による事故です。
根掛かりで失くしたルアーや釣り針が、後から来たサーファーや海水浴客の足に刺さるという事故は後を絶ちません。
・2020年 千葉県内のサーフポイントで起きた事例
海底に放置されていた大型ルアーがサーファーの足の裏に突き刺さる事故が報告されています。
釣り針には「返し」が付いているため一度刺さると抜けにくく、このケースでもサーファーは自力で外せず、消防に連絡して救急搬送されたとのことです。
錆びた針であれば、破傷風などの感染症を引き起こすリスクも伴い、非常に危険です。
注意:放置された釣り具の危険性
これらの放置された釣り具は、誰のものでもない「見えない凶器」として長期間海中に存在し続けます。
このような事故が原因で、通年で釣り禁止となった海水浴場も実在します。
これらの事故事例は、両者が常に互いの存在を意識し、安全に最大限配慮する必要があることを強く示唆しています。
それぞれのコミュニティにある暗黙のルール

THE Roots・イメージ
サーファーと釣り人の間には、それぞれのコミュニティ内部で秩序を保つために発展してきた、特有の「暗黙のルール」やマナーが存在します。
しかし、これらのルールはあくまで「内向き」のものであり、異なる活動グループとの関係を律するようには作られていません。
このことが、すれ違いや対立の一因となっています。
| サーフィンコミュニティのルール | 釣りコミュニティのルール | |
|---|---|---|
| ルールの目的 | サーファー同士の衝突回避と、波を公平に分配するため。 | 釣り人同士の場所取りトラブル回避と、安全なキャストのため。 |
| 代表的なルール | ・ワンマン・ワンウェイブ:一つの波には一人しか乗らない。 ・ピーク優先:波が最初に崩れる場所(ピーク)に最も近い人が優先。 ・ドロップインの禁止:優先権のあるサーファーの進路を妨害しない。 |
・先行者優先:先に釣りをしている人がいる場所の近くに入る際は、挨拶をして許可を得る。 ・適切な距離の確保:他の釣り人のキャスト範囲に入らないよう、十分な距離を保つ。 ・後方確認の徹底:キャストする前には必ず後方や周囲の安全を確認する。 |
| 課題 | ルールは波に乗るサーファー同士の関係を前提としており、静的な障害物(釣り人)を想定していない。 | ルールは静的な釣り人同士の関係を前提としており、動的で予測不能なサーファーの動きを想定していない。 |
・ルールのすれ違い
問題なのは、サーファーが自分たちのルールに従って「正しく」行動していても、釣り人から見れば危険な行為に映ることがある点です。
逆に、釣り人がマナーを守っていても、サーファーにとっては予測不能な障害物に見えてしまいます。
お互いのルールブックに、相手の存在が書かれていないことが、根本的なすれ違いを生んでいるのです。
サーフィンと釣りが共存するための方法
- 先行者優先という考え方は通用する?
- 海外のルールから学ぶ解決のヒント
- エリア分け(ゾーニング)の有効性
- 対話から生まれる相互理解の重要性
- 対立から協調へ、共存するための意識
- 未来のサーフィンと釣りのためにできること
先行者優先という考え方は通用する?

THE Roots・イメージ
釣り人の間でよく言われる「先行者優先」というマナー。
これは、先に釣りをしている人への敬意を示す重要な文化ですが、残念ながらサーファーとの関係においては、この考え方だけではトラブルを防ぐことはできません。
「私が先にいたんだから、後から来たサーファーが避けるべきだ」という主張は、気持ちは分かりますが、非常に危険な考え方です。
なぜなら、そこには「どちらがより危険な道具を扱っているか」という視点が欠けているからです。
前述の通り、釣り人が扱うルアーやオモリは、当たり所によっては重大な傷害をもたらす「凶器」になり得ます。
一方、サーファーは基本的に丸腰です。
万が一事故が起きた場合、法的な責任は危険物を扱っていた釣り人側が重く問われる可能性が非常に高いのです。
この「安全上の非対称性」を考えると、「先にいたから優先」という論理は通用しません。
むしろ、「危険な道具を扱っている側が、最大限の注意を払って危険を回避する義務がある」と考えるべきでしょう。
もちろん、サーファー側も釣り人に配慮する必要はありますが、最終的な安全確保の責任は、よりリスクの高い行為をしている側にあると認識することが、無用なトラブルを避ける上で不可欠です。
海外のルールから学ぶ解決のヒント
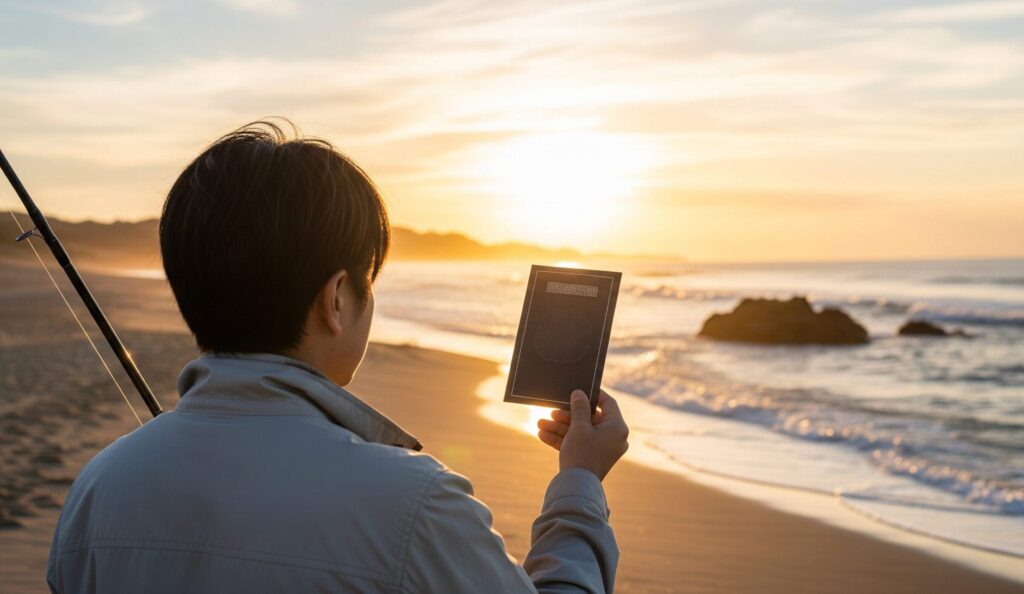
THE Roots・イメージ
日本の海岸利用が比較的自由であるのに対し、海外の多くの国では、より形式化された管理が行われています。
これらの事例は、日本の問題を考える上で重要なヒントを与えてくれます。
例えば、オーストラリアやアメリカのカリフォルニア州などでは、海で釣りをする際に原則としてライセンス(遊漁許可証)の取得が義務付けられています。
これは単なる許可証ではなく、多面的な機能を持っています。
・海外のライセンス制度の仕組み
利用者が支払うライセンス料が、水産資源の管理、調査研究、監視員の配置、そして利用者への教育プログラムといった活動の財源となります。
これは「受益者負担」の原則に基づいた、持続可能なシステムです。
さらに、ライセンス制度と連動して、非常に詳細な利用ルールが定められています。
魚種ごとに持ち帰ってよいサイズや数、禁漁期間などが厳格に規定されており、専門の監視員がパトロールを行い、違反者には高額な罰金が科されます。
このアプローチは、利用者が一定の自由を制約され、費用を負担する代わりに、より管理され、予測可能で、持続可能な利用環境が提供されるという「社会契約」に基づいています。
利用者の多様化が進む日本においても、こうした、より形式化された管理システムの導入を検討する時期に来ているのかもしれません。
エリア分け(ゾーニング)の有効性

THE Roots・イメージ
トラブルを物理的に防ぐための最も直接的な方法の一つが、エリア分け(ゾーニング)です。
これは、海岸の特性に応じて「釣り優先ゾーン」と「サーフィン優先ゾーン」を設定し、お互いの活動領域を明確にするアプローチです。
ゾーニングの具体的な方法
ゾーニングには、大きく分けて2つの方法が考えられます。
1. 空間的ゾーニング(棲み分け)
例えば、堤防や特定の岩場周辺を「釣り優先エリア」、良質な波が立つ中央部の砂浜を「サーフィン優先エリア」とする方法です。
物理的に活動空間を分けることで、予期せぬ接近や衝突のリスクを大幅に低減できます。
2. 時間的ゾーニング(時間分け)
1日の中で利用のピークが異なることを活用します。
例えば、サーファーが多くなる週末の午前中は特定のサーフブレイク周辺での釣りを控える。
逆に釣り人の活動が活発になる早朝や夕方の「マズメ時」には漁港の出入り口付近でのサーフィンを控える、といった時間単位でのルール設定です。
重要なのは「地域主導」であること
ただし、こうしたゾーニングは行政が一方的に線を引くトップダウン方式では、反発を招き形骸化しがちです。
最も重要なのは、先進事例である神奈川県小田原市のように、漁業者、レジャー利用者、行政といった全ての関係者が参加する「利用調整協議会」のような場で対話し、合意形成を図ることです。
当事者たちが自らルール作りに参画することで、そのルールへの納得感と遵守意識が高まります。
対話から生まれる相互理解の重要性

THE Roots・イメージ
ゾーニングのような「ハード」な対策と並行して、あるいはそれ以上に重要なのが、相互不信の連鎖を断ち切るための「ソフト」な対策、すなわちコミュニケーションの仕組みを構築することです。
顔も名前も知らない相手に対しては、人は攻撃的になりやすいものです。
しかし、一度でも顔を合わせて言葉を交わせば、相手を同じ人間として認識し、配慮が生まれやすくなります。
具体的なコミュニケーション施策
・合同ワークショップなどの開催
地域のサーフィン連盟と釣具組合などが共同で、定期的なワークショップなどを開催します。
経験豊富なサーファーが釣り人に波の特性を解説し、ベテランの釣り人がサーファーにキャストの危険性を説明するなど、お互いの活動への理解を深めます。
・統一された啓発サインの設置
海岸の入り口などに、両者の視点を取り入れた分かりやすい看板を設置します。
単に「~禁止」と書くのではなく、「この先、釣り人がキャストするため危険です」「このエリアはサーファーが波に乗るため接近に注意してください」のように、理由を明記し、相互尊重を促すメッセージが効果的です。
・デジタル技術の活用
自治体などが運営するウェブサイトやSNSで、ゾーニングの地図情報や定置網の設置場所、リアルタイムの波情報などを一元的に提供します。
利用者がスマートフォンで事前に情報を確認できれば、危険を予測しやすくなります。
結局のところ、ルールを作るだけでは不十分です。
なぜそのルールが必要なのかを共有し、共感の土壌を育むことが、真の共存への鍵となります。
対立から協調へ、共存するための意識
これまで見てきたように、サーファーと釣り人の間には多くの対立点があります。
しかし、両者には一つだけ、完全に利害が一致する共通の価値観が存在します。
それは、「美しく豊かな海を守りたい」という想いです。
この共通の目的を軸とした協働活動は、対立関係を乗り越え、協力関係を築くための極めて強力な触媒となり得ます。
・合同ビーチクリーンの推進
その最も代表的な活動が、合同ビーチクリーン(海岸清掃)です。
自治体やNPOが主導し、サーファーと釣り人が共に参加するビーチクリーン活動を定期的に開催します。
実際に全国各地で、サーファーや釣り人が主体となった清掃活動が実施され、協力の輪が広がっています。
同じ目的のために共に汗を流す経験は、お互いを「対立する敵」ではなく、「同じ海を愛する仲間」として認識させる効果があります。
匿名性が支配していた海岸に、個人の顔と名前を持ったポジティブな関係性が生まれるのです。
こうして醸成された信頼関係(ソーシャル・キャピタル)は、ゾーニングやルール作りといった、より利害が対立する問題について話し合う際の貴重な土台となります。
これは、低コストでありながら、両者の心理的な壁を取り払う上で非常にインパクトの大きい戦略と言えるでしょう。
【参考事例】フィッシングポイント公式サイト「サーファーと釣り人の合同クリーン作戦!!」
未来のサーフィンと釣りのためにできること
- サーフィンと釣りのトラブルは個人のマナーだけでなく構造的な問題
- 両者が同じ場所(離岸流など)を求めることが根本原因
- 釣り人にはルアーによる「加害者リスク」という恐怖がある
- サーファーには見えない釣り糸や針への恐怖と場所の独占感がある
- 実際にルアーやオモリが人体に当たり重傷を負った事故事例も存在する
- 放置された釣り具が「海の地雷」として新たな危険を生んでいる
- 各コミュニティの暗黙のルールは内向きで相互理解には繋がりにくい
- 「先行者優先」は危険物を扱う側(釣り人)の責任を免除しない
- 危険度の高い道具を持つ側が、より大きな安全配慮義務を負う
- 海外ではライセンス制度により利用が管理されているケースもある
- 物理的なエリア分け(ゾーニング)は有効な解決策の一つ
- ゾーニングは地域主導の対話によって合意形成することが重要
- 合同ワークショップなどで顔の見える関係を築き相互理解を深める
- 合同ビーチクリーンは対立を協調に変える強力なきっかけになる
- 同じ海を愛する仲間として協力し、信頼関係を築くことが全ての基本
関連記事












