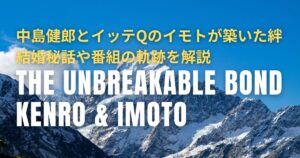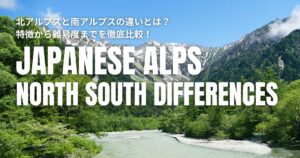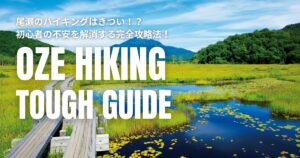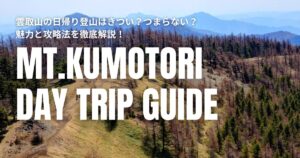- 谷口けいと中島健郎が平出和也にとってどんな存在だったのか
- K2への挑戦と滑落
- 家族と過ごした日常や家庭人としての一面
- 平出和也の死後に家族が語った想い
平出和也と谷口けい・中島健郎の軌跡
- 生い立ちと登山への転機
- 谷口けいとの出会いと運命の再会
- 中島健郎との出会いとバディ結成
- K2滑落と最後の挑戦
- ピオレドール賞の受賞歴
生い立ちと登山への転機

出典:平出和也公式Instagram
平出和也さんは、生まれ育った長野県富士見町で自然に囲まれて育ったものの、幼少期から登山に親しんでいたわけではありません。
むしろ、彼の青春時代は剣道や陸上競技、特に競歩といったスポーツに情熱を注いでいました。
高校時代には全国大会に出場するほどの実力を持ち、競技者としての道を真剣に歩んでいたのです。
ただ、大学に進学してからのある転機が、彼の人生を大きく変えます。
東海大学の山岳部に転部したのは、競歩という「他人と競い合う世界」に疑問を感じたことがきっかけでした。
誰かの背中を追うのではなく、自分自身でゴールを決めたい——その想いが、彼を登山という未知の世界に引き寄せました。
この選択は正解だったと言えるでしょう。
登山を始めてわずか1年後、2001年にはチベットのクーラカンリ東峰(標高7381m)で初登頂を果たし、早くも頭角を現します。
この成果は国内外で高く評価され、「日本スポーツ賞」を受賞するほどでした。
一方で、登山は単なる運動とは異なり、計画、判断力、精神力のすべてを必要とする活動です。
彼はそれらを学びながら、「登山とは、自分の計画や準備に対する答え合わせだ」という独自の哲学を築いていきました。
どれだけの準備をしたかが結果に直結する登山の世界は、まさに彼が求めていた場所だったのです。
このように、平出和也さんが競歩という競技から登山へと進路を変えた背景には、自己探求と成長を求める強い意志がありました。
その選択が後の世界的な登山家への道を切り開くことになります。
谷口けいとの出会いと運命の再会
平出和也さんの登山人生において、谷口けいさんとの出会いは特別な意味を持ちます。
最初の出会いは2001年、山岳関係のパーティーでのことでした。
最初は互いに深く関わることはなかったものの、2003年に運命的な再会が訪れます。
その再会の場となったのは、平出さんが勤務していた登山用品店「石井スポーツ」でした。
偶然にも谷口けいさんが来店したことをきっかけに、二人の会話が弾み、平出さんはその場で遠征への参加を持ちかけます。
谷口さんはこれに快諾し、ここから本格的なパートナーシップが始まりました。
このような流れから、2004年にはパキスタンのゴールデンピーク(7027m)への遠征を共にし、新ルートからの登頂を成功させます。
この経験を通して、二人は「同じ山を同じ目線で見上げ、同じように好きになっていく」感覚を共有し、より強い信頼関係を築いていきました。
ただし、二人の関係は単なるパートナー以上のものでした。
登山では命を預け合うことになるため、お互いの判断や感性に深く共感できなければ成り立ちません。
実際、谷口けいさんは自らを「登るほどにもっと突き進みたくなるタイプ」と語り、経験を積むことで慎重になっていく平出さんと対照的な性格でした。
それにもかかわらず、両者は互いを補完し合う理想的なバディだったのです。
2008年にはカメット峰(インド・7756m)南東壁の未踏ルートを「サムライ・ダイレクト」として初登攀し、翌年には日本人初のピオレドール賞を受賞します。
このとき谷口さんは同賞初の女性受賞者にもなり、二人の名前は世界的な注目を浴びました。
中島健郎との出会いとバディ結成

出典:石井スポーツ公式サイト
中島健郎さんと平出和也さんが登山パートナーとしてタッグを組むようになった背景には、かつて平出さんと数々の偉業を成し遂げた谷口けいさんの存在がありました。
年齢も出身地も異なる二人を結びつけたのは、山という共通の舞台だけでなく、谷口さんの言葉でした。
平出さんはある時、谷口さんから「若手で面白いクライマーがいる」と紹介されたことで初めて中島さんの名前を耳にします。
そのとき、谷口さんは「彼はセンスが良くて技術も体力もあるが、無理をしてケガをすることが多く、運が悪ければ命を落としていたかもしれない」とも話していたそうです。
平出さんはその話に「危ないやつだな」と思いつつも、どこか自分の若い頃と重ねて見ていたのです。
実際、未踏のルートに挑むには常に危険が伴います。
慎重であることはもちろん必要ですが、時には自分の限界を超える「一線」を越えなければならない瞬間もあります。
平出さん自身、その感覚をよく知っていたからこそ、「どうせ一線を越えるなら、覚悟と判断力を持って越えてほしい」と強く願っていました。
中島さんに対して「自分の背中を見て山の判断力を学んでほしい」と感じたことが、共に登る決意を固めた理由のひとつでもあります。
その後、2014年にミャンマー最高峰カカボラジ北稜での遠征を共にし、実際に同じロープで結ばれて行動する関係がスタートします。
当時の二人はまだお互いの癖や登攀スタイルを完全に理解していたわけではありませんが、極限の状況を共有することで、次第に信頼関係が深まっていきました。
本格的なバディとしての活動は2016年以降に加速し、シスパーレやラカポシなどの未踏壁を成功させていく中で、国内外の登山界から「最強のコンビ」と称されるまでになりました。
平出さんが持つ経験と判断力、そして中島さんの優れた技術と体力は、互いの長所を引き出す理想的なバランスを生んでいたのです。
また、彼らはクライマーであると同時に、山岳カメラマンとしても共通の目線を持っていました。
登攀しながら映像を撮るという過酷な状況でも、美しい山岳風景や臨場感あふれる瞬間を切り取るという使命を共に抱えていた点も、彼らの絆をより強固なものにしています。
命を預け合うパートナーシップにおいて大切なのは、単なる技術だけではありません。
同じ夢を見て、同じ危険を背負いながら、互いを尊重し信頼し続けることが不可欠です。
中島健郎さんとの出会いは、平出和也さんにとって「後進を育てたい」という願いが現実となった瞬間であり、同時に、未来を共に描ける最高のバディとの出会いでもあったのです。
K2滑落と最後の挑戦

2024年、平出和也さんと中島健郎さんが挑んだのは、世界第2位の高峰であるK2(8611メートル)の西壁でした。
この西壁は、登山界でも「最後に残された最大の課題」と呼ばれるほど困難なルートです。
過去には著名な登山家たちが何度も挑戦してきましたが、中央部からのルートは未だ誰にも攻略されておらず、その過酷さは群を抜いていました。
この難ルートに挑むにあたり、二人は通常の極地法(大量の装備と支援を使う登山方式)ではなく、最小限の装備で登る「アルパインスタイル」を採用しました。
酸素ボンベも使わず、すべての荷を自ら担いで少人数で壁に挑む方式は、より純粋で過酷な登山スタイルとされています。
この選択こそが、彼らの信念を象徴するものでした。
2024年7月27日、標高約7550メートルの氷雪壁を登攀中に事故が発生します。
氷の崩壊とともに滑落が起こり、二人は約1200メートル下まで落下したと見られています。
その後の救助活動は困難を極め、ヘリによる確認では動く気配がなく、天候や安全上の問題から捜索は7月30日に打ち切られました。
このニュースは世界の登山界に大きな衝撃を与えました。
20年かけて準備を重ねてきた夢の挑戦が、帰らぬ結果となったからです。
一方で、多くの登山家やファンが「彼らしい最期だった」とも語っています。
それは、平出さんが生涯を通じて掲げてきた「未知のルートに挑み、自らの準備を試す“答え合わせ”」という登山哲学を、最後まで貫いていたからです。
そして、今回のK2西壁登攀自体は成功には至りませんでしたが、その直前に達成されたティリチミール峰北壁での初登攀が高く評価され、2024年のピオレドール賞が追贈されました。
これは、彼らの挑戦が登頂の成否を超えた価値を持っていたことを示す証でもあります。
K2での滑落事故は痛ましいものでしたが、そこに至るまでの過程と挑戦の意味が、今なお多くの人々の心を動かし続けています。
ピオレドール賞の受賞歴
平出和也さんとそのバディたちは、世界最高峰の登山賞とされるピオレドール賞を通算4回も受賞しています。
これは日本人最多であり、世界的に見ても極めてまれな記録です。
ピオレドール賞は単なる登頂だけでなく、登山の精神性やスタイル、安全性、革新性などを総合的に評価するもので、選考は極めて厳格です。
1度目の受賞
最初の受賞は2009年、谷口けいさんとのコンビによるカメット峰南東壁(インド・7756m)の初登攀でした。
このルートは「サムライ・ダイレクト」と名付けられ、日本人として初のピオレドール受賞となりました。
谷口さんは同時に、女性として史上初の受賞者となったことでも注目を集めました。
2度目の受賞
2回目は2018年、中島健郎さんと共に挑んだシスパーレ峰(パキスタン・7611m)北東壁の初登攀によるものです。
この登山では悪天候や高所障害など多くの困難を乗り越え、登頂時には谷口さんの写真を山頂に納めるというエモーショナルな場面もありました。
3度目の受賞
3回目は2020年、同じく中島さんとラカポシ峰(パキスタン・7788m)南壁の未踏ルートに挑み、成功を収めたことによるものです。
この挑戦でも、装備を最小限に抑えたアルパインスタイルが高く評価されました。
4度目の受賞
そして4回目の受賞は2024年、死後に追贈される形で授与されました。
対象は2023年のティリチミール峰(パキスタン・7708m)北壁の「シークレットライン」と呼ばれる新ルートの初登攀です。
この功績により、平出さんは日本人初となる4度目のピオレドール受賞者となり、中島さんも通算3度目の受賞を果たしました。
これらの功績から分かる通り、ピオレドール賞は単に結果を出した登山家ではなく、「どのような信念と方法で登ったか」を問う賞です。
その中で何度も選ばれたということは、平出和也さんの登山哲学と行動が、世界の登山界において確かな評価を得ていた証でもあります。
一方で、ピオレドール賞に輝くような登攀は、常に命のリスクと隣り合わせでもあります。
過酷な環境と技術的な困難を乗り越えるためには、緻密な準備と高度な判断力、そしてバディとの深い信頼関係が不可欠です。
平出さんの受賞歴は、彼の登山家としての力量を示すと同時に、極限の挑戦に対する覚悟と誠実さを物語っています。
・関連記事:ピオレドール賞 日本人 歴代の受賞者とその功績を詳しく紹介
平出和也のカメラマンとしての顔と家族とのつながり
- クライマーとしての顔とカメラマン
- 田中陽希との共演と記録
- 遺された映像と自伝の価値
- 結婚と妻との家庭生活
- 家族が語る素顔と想い出
- お別れの会と社会への影響
- 後世へ継がれる登山の精神
クライマーとしての顔とカメラマン

田中陽希との共演と記録

出典:グレートトラバース公式サイト
冒険家・田中陽希さんとの共演も、平出和也さんの有名な活動の一部です。
平出さんは登山家としてだけでなく、山岳カメラマンとしても高い評価を受けており、その実力が発揮されたのが、田中陽希さんの日本列島縦断プロジェクトでした。
特に注目されたのは、NHKスペシャルでも放送された「グレートトラバース」シリーズです。
田中陽希さんが「日本百名山」「二百名山」「三百名山」をすべて徒歩で踏破するという壮大なプロジェクトに、平出さんはカメラマンとして全シリーズに参加しました。
この撮影には、中島健郎さんも関わっており、100名山・200名山のシリーズで撮影チームの一員として活躍しています。
登山家である二人が撮る映像は、技術だけでなく現場の臨場感や美しさを兼ね備えており、田中さんにとっても信頼できるクルーだったとされています。
ここでの撮影は、通常のドキュメンタリーとは一線を画します。
険しい山道、予測不可能な天候、長期間の行動など、撮影スタッフにとっても過酷な条件でした。
その中で平出さんは、自身も登山家である強みを活かし、困難なルートを田中さんと同じ視点・ペースで追いながら、高所からの映像やドローンなしでは撮れないアングルを自力で実現してみせたのです。
また、山の知識と経験が豊富だったことから、撮影中も田中さんと意見を交わしながら計画の柔軟な調整を行うなど、裏方としての貢献度も高かったとされています。
このように、ただ記録を残すだけでなく、プロジェクトの成功を支える「共演者」としての役割を果たしていた点が、平出さんの真の価値を物語っています。
登山家と冒険家という立場の違いを越えて、お互いに尊敬し合い、高め合う関係だったことは、視聴者にも強く印象付けられました。
こうして記録された数々の場面は、今なお多くの人にとって「自然と人の挑戦」を考えるきっかけとなっています。
遺された映像と自伝の価値
平出和也さんが残した映像と著作は、登山界にとって非常に重要な遺産となっています。
その理由は、彼の記録が「哲学と実体験の融合」であるためです。
特に、自身の登山と撮影を一体化させるという発想は、これまでの山岳記録の概念を一歩先へと進めました。
中でも代表的な著作が、自伝『What’s Next? 終わりなき未踏への挑戦』です。
この書籍は、彼の思考・準備・判断・失敗・成功までを赤裸々に語った内容になっています。
また、QRコードを読み込むことで、実際の登攀映像が閲覧できる工夫が施されており、読者は文字と映像の両方から山の世界を感じ取ることができます。
その一方で、平出さんの映像作品は、記録としての客観性だけでなく「美しさ」「感情」「命の重み」を写し取っている点で、非常に価値の高いものです。
NHKをはじめとしたドキュメンタリー番組では、彼自身がカメラを回しながら登る姿や、命がけのルート開拓の様子がリアルに映し出されています。
これにより、視聴者は山の厳しさと同時に、登山家の内面にも触れることができます。
彼の映像は登山家だけでなく、教育機関やメディアでも教材として活用されており、「どのようにリスクを管理しながら挑戦するか」という実践的な知識を学ぶための貴重な資料となっています。
平出和也さんの映像と著作は、「挑戦する人間の生き方」を後世に伝えるツールです。
見る者に問いかけ、考えさせる力を持った作品群は、今後も長く人々の記憶に残り続けるでしょう。
結婚と妻との家庭生活
平出和也さんは、数々の過酷な遠征や登山を行いながらも、一人の家庭人として穏やかな時間を大切にしていました。
冒険家というと、孤高でストイックなイメージを抱かれることが多いですが、家庭ではまったく違う一面を見せていたようです。
妻・尚子さんとの関係は、支え合い、理解し合う温かなものでした。
遠征やトレーニングで家を空けることが多い平出さんを、尚子さんは決して責めることなく見守り続けたといいます。
登山には危険が付きものですが、妻としてそのリスクを受け入れる覚悟も持ち続けていました。
日常生活では、平出さんは「最高の夫だった」と妻が語るほど、家庭内では優しく穏やかだったようです。
彼女はメディアの取材で、「冒険家ってクールで寡黙なイメージがあるけど、実際は家でとても明るく、よく笑う人だった」と話しています。
もちろん、山の現場とはまったく違う環境での家庭生活と遠征との両立には難しさもあったでしょう。
しかし、そこに無理がなかったのは、妻との信頼関係が確かだったからです。
平出さんが帰宅すれば、子どもたちと一緒に過ごす時間を大切にし、「家族との日常が、山とは違うもう一つの充電場所だった」と感じていたことがうかがえます。
また、夫婦の間では「次はどんな山に行くの?」というような、登山の計画を楽しみに聞くやり取りもあったとされます。
このような形で妻も登山を「理解する人」として寄り添っていた点は、家庭生活の支えとして非常に大きかったのではないでしょうか。
バランスのとれた家庭生活があったからこそ、平出和也さんは安心して挑戦を続けることができたのです。
家族が語る素顔と想い出
この投稿をInstagramで見る
平出和也さんが亡くなった後、印象的だったのは、ご家族が語った彼の「素顔」でした。
登山家としての平出さんは、厳しさと挑戦の象徴である一方で、家族の前ではまったく異なる人物だったことが、多くのエピソードから伝わってきます。
2024年11月、地元・長野県富士見町で行われた表彰式では、9歳の長男・志尽(しじん)くんが父親の写真を高く掲げ、「最高の父だった」と胸を張る姿が報道されました。
この姿は、多くの人の心を打ちました。
まだ幼い子供たちが、「天国でもいっぱい山登ってね」と語ったという話からも、父親に対する尊敬と愛情が深く根付いていたことがうかがえます。
家族全員が、悲しみの中にも「彼らしい最期だった」と受け入れようとする姿勢は、非常に感動的でした。
普段の平出さんは、家庭内ではよく笑い、子どもたちに対しても優しい父親だったといいます。
遠征から帰ってくると、山の話をするよりも子どもの話を聞くのが好きだったとも語られています。
このような日常の何気ない会話やふれあいが、家族にとってはかけがえのない思い出になっているのです。
前述の通り、山では常に命のリスクを背負っていた平出さんですが、家族の存在が精神的な支えであり、また彼の活動に深みを与えていたことは間違いありません。
登山家としての輝かしい功績の裏には、家族との深い絆があったことを、多くの人に知ってほしいと思います。
このように、家族が語る平出和也さんの姿は、あたたかく人間味にあふれた一人の父親としての側面も強く印象に残るものとなっています。
お別れの会と社会への影響

出典:石井スポーツ公式サイト
2024年7月、平出和也さんと中島健郎さんがK2西壁で滑落したという報せは、登山界だけでなく広く社会に大きな衝撃を与えました。
多くの人々がそのニュースに接し、驚きと深い悲しみに包まれたのは、彼らが長年にわたって登山文化をけん引してきた存在だったからです。
同年10月に東京で開かれた「お別れの会」には、およそ1500人が参列しました。
関係者向けと一般向けに分けられた式では、彼らの功績をたたえるスライドや映像が流され、多くの参列者が静かに花を手向けました。
登山界の仲間たちだけでなく、かつて彼らの映像作品や挑戦に心を動かされた人々も駆けつけていたことから、その影響力の大きさがうかがえます。
式典では、平出さんの妻・尚子さんが「彼が生きていたときと同じように、明るく楽しく生きていきたい」と語り、多くの人の胸を打ちました。
また、尚子さんは、幼い娘が「天国でもいっぱい山に登れますように」と言ったことに触れ、「これ以上、彼の人生を肯定する言葉はないと思った」と語り、参列者たちの間に深い共感と感動が広がりました。
こうした家族の言葉や振る舞いは、命と向き合う登山という行為の尊さを社会に強く訴えるものでした。
一方で、報道各社も彼らの最期を丁寧に伝え、登山の本質や生き方について改めて考えるきっかけを提供しています。
登山は一見、個人的な挑戦に見えがちですが、その過程や姿勢は社会にとって学ぶべき多くの価値を含んでいます。
平出和也さんの死がもたらしたのは悲しみだけではなく、「挑戦の尊さ」「命の重み」「残された者への希望」といった、より深い問いかけだったのではないでしょうか。
後世へ継がれる登山の精神

出典:石井スポーツ公式サイト
平出和也さんが生涯をかけて貫いた登山の姿勢は、スポーツや冒険を超えた哲学として、今後も後世に受け継がれていくでしょう。
彼が繰り返し語っていたのは、「登山は自分との答え合わせ」だという考え方でした。
これは、頂上に立つことだけを目的とせず、そこへ至る過程での計画、準備、判断力を確かめる行為こそが本質だという意味です。
この思想は、若手クライマーたちにも大きな影響を与えています。
実際に、「平出さんのような登山家になりたい」「彼の言葉が登山の考え方を変えた」という声が、SNSや雑誌などを通じて多く寄せられています。
彼の挑戦が誰かの指標となり、次の一歩を後押ししているということは、登山文化の持続と発展にとって非常に価値のあることです。
また、映像や書籍といった形で残された記録は、単なる思い出にとどまりません。
そこには、「どうすれば困難を乗り越えられるか」「なぜリスクを冒してまで登るのか」といった問いに対する、生きた答えが詰まっています。
登山をしない人にとっても、その精神は人生のさまざまな局面で応用できるヒントを与えてくれるはずです。
さらに、平出さんが語っていた「意味のないリスクはとらない」という言葉も、多くの登山者に安全への意識を促す重要な教訓として伝えられています。
挑戦することと無謀な行動は別物であり、「命を守るために登る」という姿勢が、今の登山界において一層重要視されるようになったのも、彼の影響と言えるでしょう。
今後、彼の足跡は多くの登山者によって辿られ、新たなルートとなっていくはずです。
名前の知られていない山、まだ誰も足を踏み入れていない壁——そのすべてが、彼が見ていた「次の一歩」につながっています。
こうして、平出和也さんの登山の精神は、確かに未来へと受け継がれていくのです。
平出和也の滑落と谷口けい・中島健郎との絆と挑戦を辿る:まとめ
- 平出和也は長野県出身で、競歩から登山に転身した異色の経歴を持つ
- 東海大学山岳部への転部が登山人生の出発点となった
- 登山は「自分との答え合わせ」とする独自の哲学を持っていた
- 谷口けいとは登山用品店での偶然の再会から本格的にバディを結成
- 谷口けいとのペアで未踏ルートをいくつも開拓し、世界的な注目を浴びた
- 二人は2008年にカメット峰で初登攀を成功させ、日本初のピオレドールを受賞
- 中島健郎とは谷口けいの紹介を通じて出会い、平出が後進として育てた存在
- 中島健郎とのバディ関係は2014年から始まり、シスパーレなどの登攀を成功させた
- 二人のパートナーシップは技術と経験が融合した「最強コンビ」と称された
- 2024年のK2西壁挑戦で滑落事故が発生し、二人は命を落とす
- K2西壁は世界的にも最難関とされる未踏ルートだった
- ティリチミール峰での登攀が評価され、平出の死後、4度目のピオレドールが贈られた