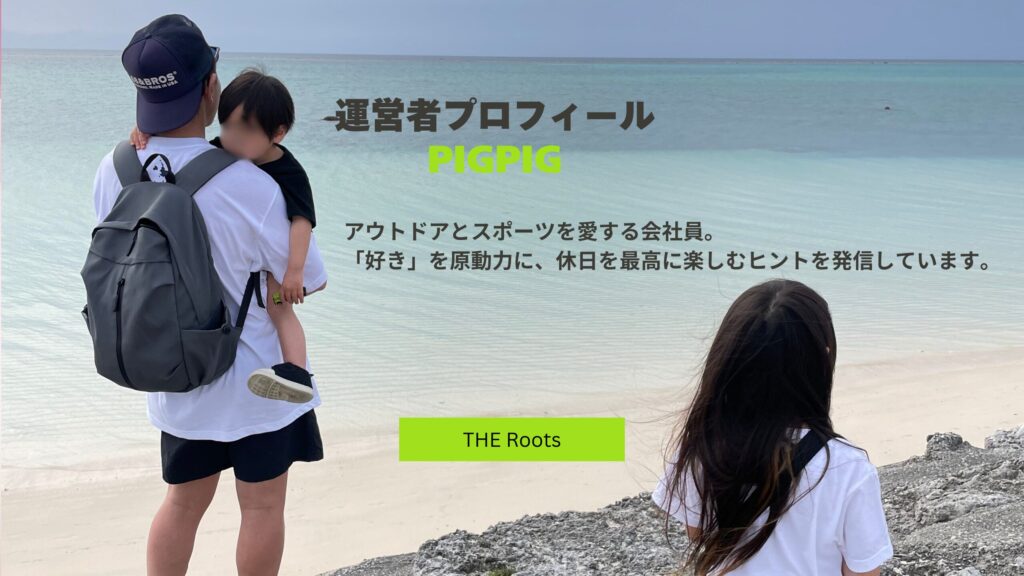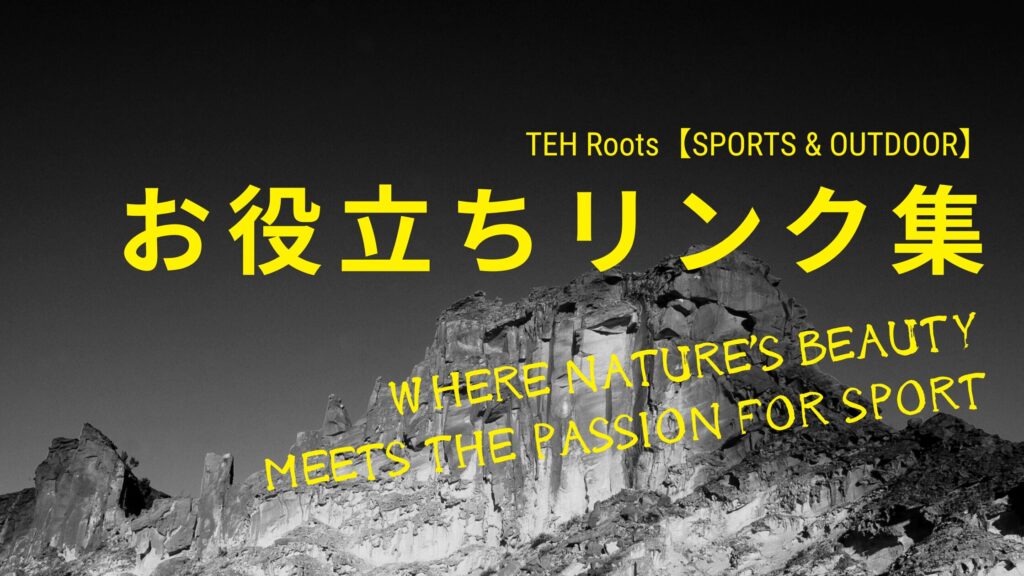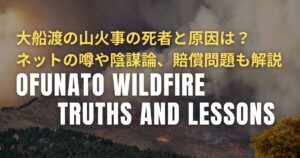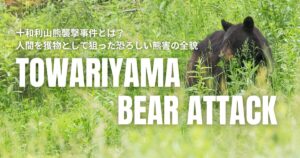みなさんは、世界最高峰エベレストのデスゾーンに、「眠れる美女」と呼ばれる登山家が眠っていたことをご存知でしょうか?
その悲劇的な物語は、しばしば「グリーンブーツ」という、もう一つの有名な道標の物語と混同されがちです。
「眠れる美女」と呼ばれたのは、女性登山家「フランシス・アーセンティエフ」
彼女はなぜ、アメリカ人女性として初の無酸素登頂という偉業に挑んだのでしょうか?
そして、なぜ登頂後に命を落とすことになったのか。
その挑戦の経緯と原因、極限状況で発したとされる最後の言葉、さらには彼女の尊厳を守るために後年行われた遺体の移動について、本記事で詳しく紐解いていきます。
また、多くの人が混同してしまう「グリーンブーツ」と呼ばれる登山家の正体にも迫ります。
これらの物語は、標高8,000メートルを超えるデスゾーンの非情な現実と、近年問題視されているエベレストの登山商業化がもたらす倫理的な課題を、私たちに静かに問いかけています。
- 眠れる美女」フランシスの遭難の経緯と原因がわかる
- 「グリーンブーツ」の正体と「眠れる美女」との明確な違い
- デスゾーンにおける救助の困難さと倫理的な問題点
- エベレスト登山の商業化がもたらした影響
エベレスト 眠れる美女の物語とその真実
- 「眠れる美女」と呼ばれたフランシスとは
- 無酸素登頂に挑んだ悲劇の経緯
- 「私を置いていかないで」最後の言葉
- 命を落とした複数の原因を分析
- 尊厳を守るための遺体の移動
「眠れる美女」と呼ばれたフランシスとは

THE Roots・イメージ
エベレストの登山史において「眠れる美女(Sleeping Beauty)」という悲劇的なニックネームで知られるようになった人物は、アメリカ人女性登山家のフランシス・アーセンティエフです。
彼女は、同じく卓越した登山家であった夫のセルゲイ・アーセンティエフと共に、登山家にとって究極の目標の一つを抱いていました。
それは、「アメリカ人女性として初めて、補助酸素(ボンベ)なしでエベレストの頂上に立つ」というものでした。
当時、無酸素での登頂は男性登山家によって達成されていましたが、女性、特にアメリカ人女性としては未踏の領域でした。
この挑戦は、単なる登頂以上の、人間の持久力と精神力の限界に挑む極めて困難で危険な試みを意味していました。
フランシスは、コロラド州テルライドで会計士として働く傍ら、夫セルゲイとロシアの山々を登るなど、情熱的な登山家でした。
「眠れる美女」という名は、彼女が亡くなった後、深刻な凍傷によってまるで磁器の人形のように見え、安らかに眠っているかのような姿で発見されたことに由来します。
しかし、その背景には壮絶な挑戦と、想像を絶する苦闘がありました。
無酸素登頂に挑んだ悲劇の経緯

THE Roots・イメージ
1998年5月、フランシスとセルゲイの夫妻はエベレストの北側(チベット側)ベースキャンプに到着し、歴史的な無酸素登頂への挑戦を開始しました。
しかし、デスゾーンの現実は彼らの前に厳しく立ちはだかります。
5月20日、彼らは最初のサミットプッシュ(頂上アタック)を試みますが、夜間の登攀に不可欠なヘッドランプの故障により、登頂を断念し引き返すことになりました。
翌5月21日、体力を十分に回復できないまま臨んだ二度目の挑戦も、わずか50〜100メートルほど進んだだけで、再び撤退を余儀なくされます。
デスゾーンでのこれらの失敗は、ただでさえ酸素が希薄な環境下で、彼らの体力を著しく消耗させ、精神的な焦りをもたらしたと考えられます。
そして5月22日、彼らは三度目の、そしてこれが最後となるサミットプッシュを開始しました。
補助酸素を使わない彼らの登攀ペースは必然的に遅く、頂上に到達したのは日没が迫る午後6時過ぎという、非常に危険な時間帯でした。
通常、安全な下山のためには午後2時頃までには登頂を終えるべきとされる中、この遅れは致命的でした。
結果として、二人は8,000mを超える極寒のデスゾーンで、予定外の夜(ビバーク)を過ごすことを余儀なくされたのです。
暗闇とマイナス30℃を下回る極寒の中での下山中、疲労困憊の二人はついに離れ離れになってしまいます。
「私を置いていかないで」最後の言葉

THE Roots・イメージ
夫セルゲイと離れ離れになり、デスゾーンに一人取り残されたフランシスは、その後、登頂を目指すウズベキスタンの登山隊によって発見されます。
彼女は半ば意識を失い、深刻な酸素欠乏と重い凍傷に苦しんでいました。
登山隊は彼女に自分たちの酸素を与え、運べる限り下まで降ろそうと懸命に試みました。
しかし、彼ら自身の酸素も尽きかけ、疲労も限界に達したため、彼ら自身の命を守るために救助活動を断念せざるを得ませんでした。
そして1998年5月24日の朝、イギリス人登山家のイアン・ウッドールと南アフリカ人のキャシー・オダウドのカップルが、登頂を目指す途中でフランシスを発見します。
彼女はまだ生きていましたが、もはや自力で動くことはできませんでした。
彼女の肌は滑らかな「乳白色」で、深刻な凍傷により、まるで「陶器の人形」のようだったと記録されています。
意識が朦朧とする中、彼女が絞り出した最後の言葉は、「私を置いていかないで (Don’t leave me)」という、人間の根源的な恐怖と助けを求める悲痛な懇願でした。
救助の断念という苦渋の決断
ウッドールとオダウドは、自らの登頂という生涯の夢をその場で諦め、マイナス30℃の極寒の中で1時間以上も彼女に付き添い、励まし続けました。
しかし、彼女の状態は絶望的であり、彼らが彼女を背負って下山することは物理的に不可能でした。
このままでは、彼ら自身の命も危険にさらされる状況でした。
最終的に、彼らはフランシスに別れを告げ、その場を離れるという、生涯にわたって彼らを苛むことになる苦渋の決断を下しました。
このエピソードは、デスゾーンにおける救助活動がいかに絶望的であるかを痛烈に物語っています。
そこでは、助けたいという強い人間的な意志が、それを絶対に不可能にする過酷な物理的現実によって、無残にも打ち砕かれてしまうのです。
命を落とした複数の原因を分析

THE Roots・イメージ
フランシスの悲劇は、単一の決定的なミスによって引き起こされたのではなく、極限状況下における複数の要因が不幸にも連鎖した結果でした。
悲劇に至った連鎖的要因
- 無酸素による極度の生理的負担: デスゾーンでは、脳の機能が著しく低下します。深刻な低酸素症(ハイポキシア)は、思考力、判断力、記憶力を奪い、しばしば幻覚さえ引き起こします。
- 致命的な登頂時刻の遅れ: 過去2回の失敗による焦りからか、安全な下山リミットである「ターンアラウンド・タイム(最終下山時刻)」を大幅に超過して登頂を強行したという、重大な判断ミスがありました。
- デスゾーンでの予期せぬビバーク: 補助酸素もテントもない状況で極寒の一夜を明かしたことにより、深刻な低体温症と、手足の感覚を失うほどの重い凍傷を負いました。
- パートナーとの離散: 極限状態でお互いを支えていた夫セルゲイと暗闇の中ではぐれてしまったことで、彼女は完全に孤立無援の状態に陥りました。
なんとか自力で最終キャンプにたどり着いた夫のセルゲイは、そこに妻フランシスの姿がないことを悟ります。
妻がまだデスゾーンに取り残されていると知った彼は、酸素ボンベと医薬品を手に取り、信じられないことに、妻を救うため再び危険なデスゾーンへとたった一人で引き返していきました。
デスゾーンの非情な掟
一度下山を始めたら、たとえパートナーが倒れていても救助のために引き返してはならない──これは、救助者も二重遭難するリスクが極めて高いため、デスゾーンにおける非情な「掟」とされています。
セルゲイの行動は、この掟を破るものであり、妻への深い愛情の証でしたが、彼自身にとっても致命的な選択となりました。
セルゲイがキャンプに戻ることはありませんでした。
彼の遺体は1年後の1999年、妻を救おうとしたルートの途中で、滑落して亡くなっているのが発見されました。
尊厳を守るための遺体の移動

THE Roots・イメージ
フランシス・アーセンティエフの遺体は、その安らかな、しかし痛ましい姿から「眠れる美女」と呼ばれ、約9年もの間、エベレスト北東稜の主要な登山ルート上で、後続の多くの登山家たちの目に触れることとなりました。
彼女の存在は、デスゾーンの危険性を伝える悲しい道標となっていました。
しかし、この状況に誰よりも心を痛め続けていた人物がいました。
1998年に彼女の最期に立ち会い、「私を置いていかないで」という言葉を聞いたイアン・ウッドールです。
その時の経験は彼に深い精神的なトラウマ(PTSD)を残し、彼はいつか彼女に尊厳ある安息の地を提供しなければならないという強い義務感を抱き続けていました。
「The Tao of Everest」遠征
その時の経験に苛まれた彼は、2007年に「The Tao of Everest(エベレストの道)」と名付けた、登頂を目的としない人道的な遠征隊を組織しました。
その唯一の目的は、フランシス・アーセンティエフに尊厳ある最後の安息の地を提供することでした。
ウッドールのチームは困難の末に彼女の遺体を発見し、星条旗で丁重に包み、登山ルートから離れた、公表されていない場所へと移し、短いセレモニーを行いました。
これにより、彼女の遺体は9年ぶりに人目から隠され、悲しい道標としての役割を終えたのです。
ウッドールのこの行動は、デスゾーンにおける倫理的責任が、山を下りた後も、あるいは何年経っても終わることがないことを示しています。
それは、人間の尊厳と記憶、そして「けじめ」についての深い物語でもあります。
エベレストの「眠れる美女」と「グリーンブーツ」の違い
- もう一つの悲劇「グリーンブーツ」とは
- 「グリーンブーツ」の正体と消えた遺体
- デスゾーンでの救助の倫理的ジレンマ
- 登山商業化がもたらした悲劇の連鎖
- まとめ: エベレストの「眠れる美女」が問いかけるもの
もう一つの悲劇「グリーンブーツ」とは

THE Roots・イメージ
「エベレストの眠れる美女」の物語は、調査する過程でしばしば「グリーンブーツ」の物語と混同されます。
その理由は、どちらもエベレストの北側ルートに長期間放置され、登山者の間で有名な「道標」となってしまっていたためです。
しかし、これらは遭難した年も、人物も、経緯も全く異なる二つの悲劇です。
「グリーンブーツ(Green Boots)」とは、エベレストの北東稜ルート、標高約8,500m地点にある石灰岩の岩窟(オーバーハングした洞窟)に横たわっていた、長年身元不明とされてきた遺体に付けられた呼称です。
この岩窟は、強風を避けられるため、多くの登山家が登頂前や下山時に一時的に休息をとり、酸素ボンベを交換する重要なポイントとなっていました。
そのため、1996年から2014年までの約18年間、登山家たちは文字通り、うずくまる彼の遺体のすぐ隣で時間を過ごさなければなりませんでした。
この事実は、デスゾーンにおける「死の日常化」を強烈に象徴しています。
その印象的なニックネームは、遺体が履いていたコフラック社製(Koflach)の鮮やかな緑色の登山靴に由来します。
両者の違いを明確に理解するため、以下の比較表にその主な情報をまとめます。
| 項目 | 眠れる美女 | グリーンブーツ |
|---|---|---|
| 本名(推定) | フランシス・アーセンティエフ | ツェワン・パルジョール(最有力) |
| 国籍 | アメリカ | インド |
| 遭難年 | 1998年 | 1996年 |
| 場所 | 北東稜、ファーストステップ付近 (約8,600m) | 北東稜、石灰岩の洞窟内 (約8,500m) |
| ニックネームの由来 | 凍傷による安らかな死に顔 | 履いていた鮮やかな緑色の登山靴 |
| 主な原因 | 無酸素・遅延登頂後の疲労、凍傷、ビバーク | 遅延登頂後、下山中に猛吹雪に遭遇 |
| 遺体の現状 | 2007年にルートから離れた場所に移された | 2014年に洞窟から移動されたと推定 |
「グリーンブーツ」の正体と消えた遺体

THE Roots・イメージ
グリーンブーツの正体を理解するためには、エベレスト登山史上、最も多くの死者を出した悲劇の一つである「1996年の大量遭難事故」に遡る必要があります。
この年、ジャーナリストのジョン・クラカワーによる著書『空へ』で有名になった南側ルートでの商業公募隊の悲劇(8人死亡)が世界的に報じられました。
しかし、あまり知られていないことに、同じ日、北側ルートでも別の悲劇が起きていました。
インド・チベット国境警備隊(ITBP)の遠征隊が、南側を襲ったのと同じ猛烈なブリザードに巻き込まれていたのです。
現在、最も広く受け入れられている説では、グリーンブーツの正体は、このITBPの隊員であったツェワン・パルジョール(当時28歳)とされています。
彼は他の2人の隊員と共に登頂成功の無線連絡をした後、下山中に嵐に巻き込まれ、消息を絶ちました。
彼が緑色のコフラック社製のブーツを履いていたことが記録と一致するとされています。
異説と論争
ただし、ITBP遠征隊の副隊長が提唱した別の説では、遺体は彼のチームメイトであったドルジェ・モルップのものである可能性も指摘されており、正体は100%確定しているわけではありません。
また、このITBP隊の遭難に関しては、当時近くを通過した日本の福岡隊の行動をめぐり、救助義務に関する論争も引き起こされました(後に誤解は解明されています)。
約20年間にわたり北壁のランドマークであり続けたグリーンブーツですが、2014年5月、その姿が岩窟から消えているとの報告が登山家たちからなされました。
これは、エベレストの登山管理を行う中国側の登山協会(CMA)または当局によって、景観と登山者の心情に配慮し、遺体が移動され、山のどこかに埋葬されたためと推定されています。
デスゾーンでの救助の倫理的ジレンマ

THE Roots・イメージ
なぜ、瀕死の登山家がいても、他の登山家は救助せずに通り過ぎてしまうことがあるのでしょうか?
その答えは、デスゾーンの過酷すぎる現実にあります。
デスゾーンの医学的現実
標高8,000mを超えると、空気中の酸素濃度は地上の約3分の1にまで低下します。
人体は細胞レベルで死に始め、MSDマニュアル家庭版の「高山病」に関する解説にもあるように、深刻な低酸素症(hypoxia)は脳機能に重大な影響を与えます。
判断力の著しい欠如、混乱、幻覚、記憶障害などが引き起こされ、合理的な思考が不可能になります。
このような状況下では、登山家は自分自身の体を支えて一歩進むだけで精一杯であり、装備を含めると100kgを超えるかもしれない動けない人間を運ぶことは、物理的にほぼ不可能なのです。
この倫理的ジレンマを象徴するのが、2006年に起きたイギリス人登山家デイビッド・シャープの事件です。
彼はまさに「グリーンブーツ」が横たわるその洞窟で低体温症と低酸素症に陥り、助けを求めてうずくまっていました。
しかし、その日、登頂を目指す40人以上の登山家が、まだ息のある彼を横目に通り過ぎていったのです。
彼はその後、死亡しました。
この事件は世界中から厳しい非難を浴びましたが、現場にいた登山家たちは「彼をグリーンブーツの遺体と誤認した」「助けようがなかった」と証言しています。
これは登山家が冷酷だからという単純な話ではありません。
「サミット・フィーバー」と呼ばれる、登頂への強迫的な渇望が合理的な思考を麻痺させる心理状態も影響します。
一方で、フランシス・アーセンティエフのケースが示すように、自らの登頂という目標を犠牲にしてでも他者を助けようと試みる登山家も存在します。
デスゾーンにおける倫理とは、善か悪かという二元論で語れるものではなく、低酸素状態の脳が下す、一連の不可能な選択の結果とも言えるのです。
登山商業化がもたらした悲劇の連鎖

THE Roots・イメージ
1996年の大量遭難事故や、2006年のデイビッド・シャープの悲劇は、1990年代以降に加速したエベレスト登山の「商業化」がもたらした影の部分であるとの見方が強いです。
「商業公募隊」が一般的になったことで、莫大な費用(数百万〜一千万円以上)を支払えば、十分な経験がなくともガイドやシェルパの強力なサポートを受けて登頂を目指せるようになりました。
その結果、登山者の数は爆発的に増加しました。
この登山者の急増が引き起こしたのが、ルート上の難所(ボトルネック)での深刻な「渋滞」です。
特に2019年にヒラリーステップ(現在は崩壊)付近で撮影された長蛇の列の写真は、世界に衝撃を与えました。
この渋滞は、ただ待たされるだけでなく、貴重な補助酸素を浪費し、体温を奪い、安全な下山時刻を大幅に遅らせるという、文字通り致命的なリスクをもたらします。
顧客は高額な費用を支払っているため、登頂への期待と圧力は極めて高くなります。
この経済的な力学が、悪天候や体調不良、あるいは渋滞による遅延があっても、「引き返す」という安全のための合理的な判断を鈍らせる一因となっているのです。
(参考記事:AFPBB News「商業登山の闇、エベレスト登頂という「賞杯」に懸けるリスク」)
また、デスゾーンからの遺体回収は、数万ドル(数百万円以上)の高額な費用がかかるだけでなく、救助にあたるシェルパたちの命を危険に晒す、極めて困難な作業となります。
ヘリコプターはこの高度では活動できず、すべて人力に頼らざるを得ないため、多くの遺体が「回収不能」として山に残され続ける結果となっています。
まとめ: エベレストの「眠れる美女」が問いかけるもの
- 「眠れる美女」はアメリカ人女性フランシス・アーセンティエフ
- 彼女は1998年にアメリカ人女性初の無酸素登頂を目指し遭難した
- 夫セルゲイも妻を助けるために引き返し命を落とした
- 遭難の原因は無酸素による疲労、登頂の遅れ、デスゾーンでのビバーク
- 「私を置いていかないで」が彼女の最後の言葉として記録されている
- 遺体は9年間ルート上にあったが2007年にイアン・ウッドールにより移設された
- 「グリーンブーツ」は鮮やかな緑色の靴が由来の別の遺体
- 正体は1996年に遭難したインド人登山家ツェワン・パルジョールが最有力
- 「グリーンブーツ」は1996年から2014年まで約18年間ランドマークとなっていた
- 「グリーンブーツ」の遺体も2014年に岩窟から移動されたと推定される
- この二つの悲劇はしばしば混同されるが全く別の物語である
- デスゾーンは酸素が地上の3分の1しかなく救助活動は物理的にほぼ不可能
- 2006年にはデイビッド・シャープが40人以上に見過ごされ死亡する事件も起きた
- 登山の商業化が高額な費用と引き換えに登頂への圧力を生んでいる
- ルート上の「渋滞」が致命的な遅延を引き起こす原因となっている
関連記事
なぜ漫画『岳』は心を揺さぶるのか?お得な読み方もネタバレなしで解説
植村直己の死因は?遺体はなぜ見つからないのか?原因と経緯を解説